国民年金
国民年金
国民年金に加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
加入者(被保険者)は次の3種類に分かれます。
| 加入者の種類 | 内容 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合に加入していない方(自営業者、農林漁業者、学生、フリーアルバイター等) |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険に加入している方(会社員、公務員等) |
| 第3号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合の加入者(第2号被保険者)の扶養家族になっている配偶者 |
このほかにも、希望すれば加入できる(任意加入被保険者)制度があります。この任意加入制度は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人や日本国籍で海外に住所がある20歳以上65歳未満の人は、加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳までの加入で老齢基礎年金の受給資格がない人は、70歳まで加入できます。
国民年金の届出
| このようなとき | 届出 | 添付書類(必要なもの) |
|---|---|---|
| 60歳までに会社員や公務員でなくなったとき(退職したとき) | 国民年金加入の手続 |
|
| 会社員や公務員の夫(妻)の扶養でなくなったとき | 3号被保険者から1号被保険者への変更手続き |
|
| 65歳になったとき(第1号被保険者期間のみの方) 〈注1〉 | 老齢基礎年金の受給手続き |
|
| 障害者の認定を受けたとき(初診日が第1号被保険者の方) | 障害基礎年金の受給手続き |
|
| 年金受給者の住所や年金受取金融機関が変わるとき | 変更届を提出 (保険医療課または明石年金事務所) | 保険医療課または市民課にある変更届を提出してください。(日本年金機構でマイナンバーを把握している方は、住所変更手続きは不要) |
| 年金受給者が死亡したとき |
死亡届・未支給請求書を提出(明石年金事務所) ※老齢基礎年金受給者は保険医療課へ提出 |
受給者
|
〈注1〉60歳になったら、資格を喪失します。手続きは必要ありません。老齢基礎年金は、65歳から支給となるので、この機会に納付月数等を調べることをお勧めします。満額の老齢基礎年金額に至っておらず年金を増額する場合は、任意加入制度が利用できる場合があります。
〈注2〉添付書類は、請求者のマイナンバーを記入いただくことで省略できます。
国民年金の保険料
保険料の額
令和7年度の国民年金定額保険料は、月額17,510円です。付加保険料は月額400円です。
付加保険料とは、定額保険料に月額400円をプラスして納めることで、老齢基礎年金額に上乗せされます。2年間で納めた保険料と同額となり、受け取る付加年金額は、定額のため物価スライド(増額・減額)しないのでお得です。
保険料の前納制度
保険料を納期前に一括で前払いすると保険料が割引になる「前納制度」があります。
|
|
割引後の口座振替額 | 定額の保険料 | 割 引 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 口座振替 |
現金納付 クレシ゛ット納付 |
|||
| 通常(翌月末振替納付) | 17,510円 | 17,510円 | - | - |
| 早割 (当月末) | 17,450円 | 17,510円 | 60円 | - |
| 6カ月 前 納 | 103,870円 | 105,060円 | 1,190円 | 850円 |
| 1年 前 納 | 205,720円 | 210,120円 | 4,400円 | 3,730円 |
| 2年 前 納 | 408,150円 | 425,160円 | 17,010円 | 15,670円 |
保険料の納付期限は、翌月末日までとなっています。口座振替での前納が便利でお得です。「前納制度」の申し込みについては、提出期限をご確認ください。詳しくは下記、日本年金機構のホームページへ
国民年金の加入と保険料のご案内 ・20歳になられた方向けのご案内です
保険料の納付方法
日本年金機構から送付される保険料納付書で、指定された期日までに金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いください。
また、口座振替やクレジットカードにより納付される場合は、金融機関・保険医療課または年金事務所に備え付けの申込用紙で手続きを行ってください。令和5年2月からスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができます。スマホ決済は、対応する決済アプリをフマートフォン等の端末にインストールしたうえ、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができます。対象決済アプリ等の詳細については、日本年金機構のホームページで確認してください。
保険料の免除制度
経済的に保険料の納付が困難なときは、申請し承認されると納付が免除される制度があります(申請免除)。失業・倒産・事業の廃止等を理由として申請するときは、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等)の写しを添付してください。事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方については、申し立て書類が必要となります。
1.総合支援資金の貸付決定通知書の写しとその申請をした時の添付書類の写し
2.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
3.税務署等への異動届出書、開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(受付印有り)
4.保健所への廃止届出書の控(受付印有り)または廃止届証明書
5.その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類
申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。また、50歳未満の方で本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば納付が猶予される「納付猶予制度」もあります。
所得がない学生の方は、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が利用できます。
審査の結果、免除・納付猶予にならない場合もあります。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
- 免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
注釈:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
- 産前産後期間の取り扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
- 届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
- 届出先
保険医療課(庁舎1階)
日本年金機構ホームページからも届出用紙をダウンロードすることができます。
また、記入の方法も併せて掲載されています。
また、届出の際は、以下の書類をご用意ください。
- 添付書類について
出産前に届出をする場合:母子健康手帳
出産後に届出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要
( ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書 など出産日および親子関係を明らかにする書類 が必要です。)
国民年金保険料の納付申出制度
現在、障害年金の受給などにより国民年金保険料の法定免除を受けている方も、本人の申出によって、保険料を納付できるようになりました(納付申出制度)。この制度をご利用いただくと、保険料の口座振替や、前納による保険料の割引など、便利でお得な制度もあわせてご利用いただけます。
障害基礎年金と老齢基礎年金は、どちらか一方しか受けることができないため、生涯にわたり障害基礎年金が受けられる方は、原則として保険料の納付は不要です。しかし、障害が軽快する可能性のある方は、将来障害が軽快して障害基礎年金が受けられなくなった場合、老齢基礎年金を受けることになるので、そのような場合に受給する老齢基礎年金を増やすために保険料を納付することができる制度です。
「ねんきんネット」であなたの年金情報が確認できます
「ねんきんネット」とは、年金加入者の方が、自身の年金加入記録や将来の年金受給見込額を確認できるインターネットサービスです。すでに年金を受給している方は、年金加入記録のほか、引越し等の住所変更時に日本年金機構への届けが必要かどうかを確認することもできます。
なお、インターネットのご利用が難しい方は、保険医療課窓口で無料で確認いただけます。(1)本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)と、(2)基礎年金番号または照会番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書または年金定期便等)をお持ちください。
ねんきんネットでは、共済組合等の加入期間については表示されません。
国民年金基金のご案内
国民年金基金は、国民年金に上乗せする公的な個人年金です。
自営業者などの国民年金第1号被保険者の方が将来受給する年金は『老齢基礎年金』だけですが、厚生年金に加入している方は『老齢基礎年金』に『厚生年金』が上乗せされます。この差を埋めるために創設されたのが、国民年金基金です。
国民年金基金に加入すれば、自営業者などの方々の年金も「国民年金」と「国民年金基金」の「二階建て」の仕組みになり、ゆとりある老後資金を準備できます。
(お問い合わせ先)
加入申出に関する相談先 電話0120-65-4192(フリーダイヤル)
詳しい内容は、国民年金基金ホームページをご覧ください。
明石年金事務所 年金相談のご案内
●年金受給(完全予約制)に関するご相談について、下記へ申し込んでください。
- 申込方法は、明石年金事務所 お客様相談室(電話番号 078-912-4983)へ直接電話でお申し込みください。
- 申し込みの際は、対象者の氏名・生年月日・基礎年金番号・住所および相談内容をお伝えください。
- 小野市で実施していた「出張年金相談」は令和7年4月以降は実施されません。
●一般的な年金相談に関するお問い合わせは『ねんきんダイヤル』へ
ナビダイヤル 0570-05-1165
(受付時間) 月 曜 日 午前8時30分~午後7時
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで
●来訪相談のご予約は『予約受付専用電話』へ
ナビダイヤル 0570-05-4890
(受付時間)月~金曜日(平日) 午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は利用できません。
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
【支給要件】
- 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者であること
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の年金収入額とその他の所得の合計額が、889,300円以下であること
- 障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
【支給要件】
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得額が、「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注1)」以下であること
- (注1)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)
(050で始まる電話からは03-6700-1165)
・明石年金事務所:078-912-4983
「年金個人情報流出」を口実とした“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
日本年金機構の個人情報流出問題で、不審な電話がかかってくる事例が発生しています。日本年金機構や市から直接電話でお知らせすることはありませんのでご注意ください。
詳しくは、下記、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 市民協働部 保険医療課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0500
ファックス:0795-42-5282
メールフォームによるお問い合わせ







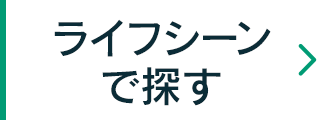
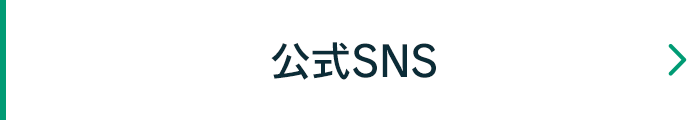



更新日:2025年04月01日